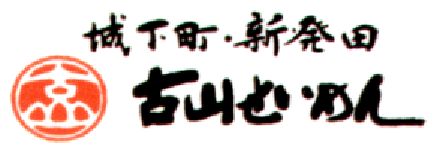ー餃子の皮は常温で使うことがポイント!おいしい餃子の作り方まとめー
餃子を作るときには、餃子の皮にこだわることがポイントです。
例えば、餃子の皮は常温に戻してから使うと上手に包めます。
また、餃子の皮を自作するときには常温で寝かせると、きれいに形成できるでしょう。
この記事では、餃子の皮について解説します。
餃子の包み方のポイント4つ
餃子を皮で包む作業は、「折り紙や粘土細工のようで楽しい」と感じる方は多いのではないでしょうか。
その一方で、包んでいると餃子の皮が破れてしまったり、形が歪になってしまったりして、難しいという声もよく聞きます。
そこで、上手に包むための餃子の皮で餡を包むときのポイントを4つ見てみましょう。
次のポイントをおさえれば、うまく包めるでしょう。
1.餃子の皮を常温に戻す
餃子を包むときのポイントは、冷蔵庫で保存していた餃子の皮を常温に戻してから使うことです。
スーパーなどで販売されている餃子の皮も、冷蔵されていることが多いので、買ってきたばかりなら常温してから使いましょう。
常温で戻せば、皮がやわらかく伸び、包みやすくなります。
逆に、冷えたままの餃子の皮は硬いため、破れてしまうことも。
餃子の皮を触ってみて冷たくなく感じなければ常温に戻っており、表面温度は20度前後が目安です。
2.肉餡を寝かす
肉餡は、包む前に冷蔵庫で寝かせることが大切です。
肉餡をすぐに餃子の皮で包んで焼くと、肉が縮んでしまい歯ごたえが硬くなってしまうためです。
1時間から3時間ほど肉餡を寝かせれば、食材の水分が肉に行き渡るため、焼いても縮みにくくなるうえ、味も馴染みます。
また、冷蔵庫で寝かすことで肉の脂肪分が固まるので、包みやすくなるでしょう。
3.肉餡をのせすぎない
餃子の皮で肉餡を包むときには、つい肉餡をのせすぎてしまうという方は多いかもしれません。
しかし、餡が多いと皮が閉じにくくなるばかりか、焼いているうちに破れたり餡がはみ出したりして、見栄えが悪くなってしまいます。
餡の適量は餃子の皮の大きさにもよりますが、デザートスプーン一杯分が目安です。
「餡が少し少ないかな?」と感じても、包んでみると適量であることがわかるでしょう。
餡は餃子の皮の中央に平らに伸ばすようにのせるのもポイントです。
4.餃子の皮は優しく扱う
包むときには、餃子の皮を優しく扱うことも上手に包むコツです。
皮を引っ張ってしまうと、皮が薄くなり破れてしまう原因に。
片方のサイドから順に、折り目をつけながら軽くつまむようにして閉じます。
ギュッと指先に力を入れて閉じるのではなく、軽く力を入れる程度にとどめておきましょう。
餃子の焼き方のポイント5つ
次からは、餃子を焼くときのポイントを5つ紹介します。
仕上がりが格段に変わりますので、ぜひお試しください。
1.油をたっぷりひく
餃子を焼くときには、フライパンにたっぷり油をひくと、餃子の皮がフライパンにくっついてしまうのを防げ、パリッとした皮のおいしい餃子が作れます。
テフロン加工のフライパンなら、餃子の皮がフライパンにくっつきにくく使いやすいでしょう。
鉄のフライパンを使うときには、充分にフライパンを温めておくとくっつくのを防げます。
なお、油の目安は、鍋底から1mmから2mmほどです。
2.油を30秒熱する
フライパンに油をひいたら、すぐに餃子を入れてはいけません。
火で油を30秒熱してから餃子をフライパンに並べることが重要です。
しっかり熱した油が、餃子の皮から染み出した水分を一気に飛ばしてくれ、餃子の内部にまんべんなく熱が通ります。
3.熱湯を入れて蒸し焼きする
一般的には、餃子を焼き始めてしばらくしたら、フライパンに水分を入れて蓋をし、蒸し焼きにします。
このときに水ではなく熱湯をフライパンに注ぐことがポイント。
水を入れるとフライパン内部の温度が下がり、皮がパリッと焼き上がらず、食感が悪くなってしまうためです。
熱湯の量は餃子10個で80mlが目安です。
4.フライパンを揺する
蒸し焼きにしているときには、フライパンを前後に揺りましょう。
そうすることで、焦げ付きを防げます。
激しく揺らすと餃子が崩れるため、優しく揺するようご注意ください。
5.最後は強火で30秒加熱する
餃子を蒸したら、蓋を外してさし油をして強火で30秒加熱します。
そうすることで、餃子の皮がパリッと仕上がります。
油の量は餃子10個に対して大さじ半分ほどが適量です。
なお、さし油はごま油がおすすめ。
ごま油の香ばしい香りを楽しめます。
餃子の皮を自作するには?
市販の餃子の皮を使うのではなく、自作するのも手です。
自作すれば、自分好みの厚さに調整できますし、より餃子作りを楽しめるでしょう。
材料は小麦粉とぬるま湯、塩だけですので、特別な材料を買い揃える必要もありません。
興味のある方は、餃子の皮を作ってみてください。
【材料】
強力粉:100g
薄力粉:100g
ぬるま湯:100cc
塩:ひとつまみ
【作り方】
1.ボウルに強力粉と薄力粉、塩を入れてからぬるま湯を加えて、箸などで混ぜる
2.1の生地がまとまったら、手で練る
3.生地に光沢が出たらラップで包むかビニール袋に入れて、20分常温で寝かせる
4.生地を棒状に形成して、24個に分ける
5.分けた生地を軽く潰し、打ち粉をして綿棒で伸ばす
※綿棒は中心から外側に向けて動かすのがポイント
餃子の皮で使用する小麦粉は、
・強力粉を多めに使用する
・餃子の皮で使用する小麦粉の種類を変える
・小麦粉の一部を米粉にする
…などアレンジをするのもおすすめです。
また違った味や食感に仕上がります。
詳しくは、以下の記事もチェックしてみてくださいね。
余った餃子の皮は常温ではなく冷凍保存が鉄則
餃子の皮が余って保存するときにもコツがあります。
それは、常温や冷蔵庫で保存するのではなく、冷凍すること。
常温保存では、カビの発生や腐敗のリスクが高いですし、冷蔵庫で保存すると乾燥し破れてしまう場合があります。
また、皮同士がくっついてしまい、使うときに剥がしにくくなります。
冷凍庫で保存すれば、餃子の皮内部の水分を保てます。
次のポイントを踏まえて餃子の皮を保存すれば、食感が損なわれずに済むでしょう。
餃子の皮はラップで包む
餃子の皮は乾燥しやすいため、必ずしっかりラップで包んで保存します。
数枚ずつ小分けしてラップで包むと、くっついても剥がしやすいでしょう。
ラップで包んだ餃子の皮は、さらに冷凍用の保存バッグに入れて空気を抜いてから口を閉じます。
空気が入ったまま冷凍してしまうと、品質が落ちてしまうので、しっかり空気を抜くことが大切です。
冷凍保存した餃子の皮も、もちろん常温に戻してから使ってくださいね。
まとめ
こうしてみると、餃子の皮は常温で戻してから使う、皮自作するときは生地を常温で寝かせる、保存は冷凍するなど、餃子の皮の扱いには温度が重要なことがわかるのではないでしょうか。
また、餃子を焼くときにも少し手間を加えるだけで、お店で食べるようなおいしい餃子を自宅で作れます。
温度に注意して餃子の皮を扱えば、特別な技術は必要ありません。
ぜひ、試してみてくださいね。

新潟県新発田市のめん類・餃子の皮・焼売の皮などの製造業は有限会社古山製麺所に お任せください
会社名:有限会社古山製麺所
住所:〒957-0356 新潟県新発田市岡田1807
TEL:0254-22-2225
FAX:0254-24-8523
営業時間:8:00~17:00
定休日:木曜・日曜
対応エリア: 新潟県新発田市
業務内容:めん類(中華麺・うどん・日本そば)・餃子の皮・焼売の皮・ワンタンの皮・春巻きの皮などの製造業